| 項目 | 特養(特別養護老人ホーム) | 老健(介護老人保健施設) |
|---|---|---|
| 目的 | 長期的な生活の場(終の棲家) | 在宅復帰を目指す一時的な施設 |
| 利用期間 | 基本は終身利用 | 原則3ヶ月(延長あり) |
| サービス内容 | 生活支援・介助が中心 | 医療・リハビリが充実 |
| 入居条件 | 要介護3以上 | 要介護1〜5まで対応 |
| 医療体制 | 医師は非常勤(外部連携) | 医師・看護師が常駐 |
| 費用目安 | 月額8〜13万円程度(安め) | 月額9〜20万円程度(やや高め) |
| 入居しやすさ | 待機者多く時間がかかる | 比較的入居しやすい |
「特養と老健って、どう違うの?」──そう感じたときは、きっと誰かの入所を本気で考えるタイミングですよね。

けれどこの2つ、名前は似ていても、
- 目的
- 入所条件
- 滞在期間
- 医療・費用面
…実は、根本的にまったく違います。
なのに、十分に違いを知らずに選んでしまい、「こんなはずじゃなかった」と後悔するご家族が少なくありません。
私も、母と父の介護を通して──この2つの施設がいかに別物なのかを痛感しました。
最初に違いを理解していたら、どれだけ安心できただろうか…と思ったほどです。
読み終える頃には、「うちの家族に合っているのはどちらか?」が自信をもって判断できるはずです。どうぞ、最初の比較からご覧ください。
特養と老健の違いとは?|目的と役割を根本から理解する
特養は「生活の場」、老健は「一時的なリハビリの場」。両者はそもそも目的がまったく違い、施設での暮らし方も大きく異なります。
「特養と老健って、どちらも介護施設でしょ?」──確かにどちらも介護保険施設ですが、目的はまるで違います。

まず、それぞれの施設がどんな“役割”を担っているのかを整理しましょう。
| 項目 | 特養(特別養護老人ホーム) | 老健(介護老人保健施設) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 長期的な介護生活の支援(終の棲家) | 在宅復帰を目的としたリハビリ |
| 対象者 | 介護が常時必要で自宅生活が難しい高齢者 | 退院後のリハビリや在宅準備が必要な高齢者 |
| 滞在期間 | 長期(制限なし) | 原則3〜6ヶ月程度の短期 |
| 特徴 | 生活重視/医療体制は限定的 | 医師・リハビリスタッフ常駐/医療体制強め |
これがまさに、施設の“そもそもの違い”。
- 短期で戻す前提なのが【老健】
- ずっと暮らすことを前提にしたのが【特養】
ここを理解せずに選んでしまうと、「数ヶ月で出なきゃいけなかった」「こんなに医療が弱いなんて知らなかった」…という“思ってたのと違う”が起きてしまうんです。
特養と老健に入れる条件は?|要介護度と申込み基準の違い
特養は原則「要介護3以上」、老健は「要介護1〜」でも入所可能。
認知症などの症状があっても、要介護度が低いと特養には申し込めないケースがあるため注意。
施設を選ぶ前に、まず確認しておきたいのが「そもそも入れるのかどうか」という条件。

とくに【要介護度】は、特養・老健ともに入所可否を決める重要なラインです。
| 項目 | 特養(特別養護老人ホーム) | 老健(介護老人保健施設) |
|---|---|---|
| 要介護度 | 原則「要介護3以上」 | 「要介護1以上」ならOK |
| 入居条件 | 常時介護が必要/在宅生活が困難 | リハビリによって在宅復帰を目指せる状態 |
| 備考 | 要介護2以下は原則対象外(例外あり) | 医療ケア・リハビリが整っていれば柔軟に対応可能 |
認知症があるから特養に…と思っても、要介護2以下なら門前払いされるケースも少なくありません。
実際、私の母も「要介護2」で特養に申し込もうとしましたが、「制度上、原則お受けできません」と断られました。
そのとき紹介されたのが【老健】。短期的でも受け入れてくれて、回復のチャンスを得ることができました。
【判断の目安】
・要介護1〜2 → 老健を中心に検討
・要介護3以上 → 特養の申し込みが可能
介護認定の結果をまず確認することが、正しい施設選びの第一歩になります。
特養と老健の入所期間はどう違う?|「ずっと住める」と「一時的な滞在」の違いに注意
特養は「長期入所(基本は終身)」、老健は「原則3〜6ヶ月の短期滞在」。
老健は“在宅復帰を前提”とした施設なので、長く居続けることは基本的にできません。
施設を選ぶうえで、「どれくらいの期間、住めるのか?」は家族の生活設計にも大きく関わる大事なポイントです。

| 項目 | 特養(特別養護老人ホーム) | 老健(介護老人保健施設) |
|---|---|---|
| 入所期間 | 長期(基本的に終身OK) | 原則3〜6ヶ月程度 |
| 制限の有無 | 制限なし(ただし待機者多い) | 目的達成後は退所が原則 |
| 退所タイミング | ご本人の状態や希望次第 | 回復・リハビリ完了時に退所案内あり |
【判断ポイント】
・今後ずっと暮らす施設が必要 → 特養
・まずは一時的な回復を目指したい → 老健
老健はゴールじゃなく、次の選択への“中継点”。「その後、どこへ行くか」まで想定しておくことが大切です。
特養と老健、費用の違いは?|月額費用の相場と“あとから高くなる落とし穴”に注意
- 初期費用はどちらもほぼ0円でスタート可能
- 月額は大きな差はないが、老健は医療加算・リハビリ費で増額リスクあり
- 長期滞在でトータルコストを考えるなら、特養は安定しやすい
施設選びで気になるのが、「結局、月にいくらかかるの?」という費用の話。
実はこの2つ、制度上は大きな差はないものの運用や医療対応によっては、かなり負担が変わってくるんです。

| 項目 | 特養(特別養護老人ホーム) | 老健(介護老人保健施設) |
|---|---|---|
| 月額費用(目安) | 約7〜12万円前後 | 約8〜13万円前後 |
| 初期費用 | 基本的になし | 基本的になし |
| 医療・リハビリ加算 | 少ない | 多い(治療や処置が多いと加算) |
| 入所期間による累積 | 長期滞在で安定 | 短期滞在+次の転居で費用がかさむ場合あり |
施設選びでは、「今月いくらかかるか?」だけでなく、「この先いつまで、いくら払い続けるのか?」という累積視点が大切です。
特養と老健、どちらが向いている?|あなたの家族に合った選び方まとめ
✔ 長期入所・生活支援が必要な人は【特養】
✔ 医療ケアやリハビリが必要で短期滞在なら【老健】
入所の目的・要介護度・医療ニーズ・費用の視点から、自分の家族に合う施設を判断するのが重要です。
ここまで、特養と老健の違いを目的・条件・期間・費用・医療・設備…あらゆる視点で比較してきました。
では、実際にどちらを選ぶべきなのか?ここで、総まとめとして判断ポイントを整理しておきましょう。

| 判断ポイント | 特養が向いている人 | 老健が向いている人 |
|---|---|---|
| 入所の目的 | 長期的な生活支援が必要 | 一時的にリハビリして在宅復帰したい |
| 要介護度 | 要介護3以上 | 要介護1以上(柔軟に受け入れ) |
| 医療体制 | 最低限でOK | 処置や観察が必要 |
| 滞在期間 | 基本は終身OK | 原則3〜6ヶ月の短期 |
| 居室・環境 | 家のような落ち着きがほしい | 病院的でも問題ない |
| 予算感 | 長期的なコスパ重視 | 一時的でも構わない |
「長く安心して暮らしてほしい」「ちゃんとリハビリして回復してもらいたい」「医療処置ができるところじゃないと不安」
家族が本当に求めていることは何なのか?目先の空き状況や立地に流されずに、“目的”を優先して選ぶこと。
- 介護認定を見直す
- 地域のケアマネ・施設相談員に状況を伝える
- 実際に見学して、家族で判断する
この記事が、あなたとご家族の“正しい選択”の一歩になればうれしいです。どんな選択でも、後悔しないために──知ることから始めましょう。
居室や設備の違い|特養と老健で“暮らし心地”はどう変わる?
特養は「住む場所」なので生活重視、老健は「一時滞在」なので病院的な設備が多め。
居室のタイプやプライバシー、雰囲気も大きく違うため、事前の見学は必須。
施設の「目的」が違えば、当然ながら建物のつくりや雰囲気も別物です。実際、見学してみると「まるで違うな」と感じる方がほとんど。
| 項目 | 特養(特別養護老人ホーム) | 老健(介護老人保健施設) |
|---|---|---|
| 居室タイプ | ユニット型個室 or 多床室 | 個室・多床室が混在 |
| 雰囲気 | 生活の場として落ち着いた空間 | 病院に近い雰囲気(白・無機質) |
| 共有スペース | 居間、談話室など生活空間が充実 | 食堂・機能訓練室など機能的 |
| 設備の特徴 | 入浴・トイレ・キッチンが生活ベース | リハビリ器具・処置室など医療寄り |
・長く住む=環境の居心地は超重要 → 特養
・短期滞在=機能優先でOK → 老健
どちらも実際に見学して、「自分(or 家族)がここで過ごせそうか?」を肌で感じることが大切です。
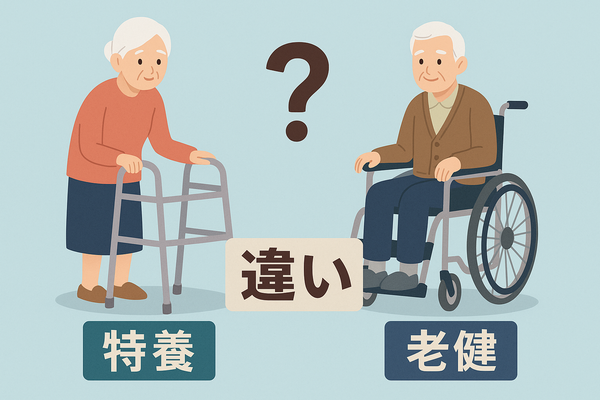








コメント